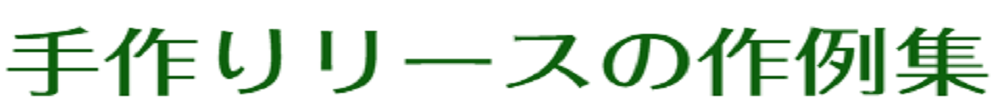◆ススキのリース
ススキのリースの作り方

西洋ススキ=パンパスグラスのリースの方が良く見かけますが、ススキのリースも同じように作れます。ただ、パンパスグラスの方が毛足が長く、穂もたっぷりしているので、パンパスならば1本あれば簡単にボリュームが出せるのに、ススキで同じ嵩を出そうとすると、膨大な本数が必要になります。
たまたま、手元にススキの乾いた穂が4本あったので、4本の嵩でできる小さなリースを作ってみました。ものすごく小さく作ったので、あっという間にできました。
【目次】
1.使用したもの
2.ワイヤーでリースの枠を作る
3.ススキの穂を、テグスで取り付ける
4.微調整して、出来上がり
使用したもの
以下のようなものを使用しました。
- ススキの穂……乾いたものを4本
- テグス
- リボン(吊り下げ用)
- ワイヤー
- 鋏
ワイヤーでリースの枠を作る
ススキの穂が、4本分しか無かったので、ほんの小さなリースしかできないだろうと思いました。

すごく小さいリース枠になりそうなものが手近に無かったので、ワイヤーで作ることにしました。手持ちのクラフトワイヤーを、空き瓶に二周巻き付けて、

ぎゅっと引っ張って、円形になるように癖付けし、ずれないようにセロテープで固定したのが下の画像です。

大胆にセロテープで貼っているのは、どうせススキを付けたら見えなくなるからです。
使っているワイヤーは、すごくやわらかいものです。普通、ワイヤーだけをリースベースにするときには、あまりにも細いorやわらかいワイヤーは、吊っているうちに重さで「円」が「楕円」に伸びてしまうので使えないのですが、今回のススキのリースは、取り付けるパーツが軽いので、安心してやわらかめのワイヤーを使っています。
ススキの穂を、テグスで取り付ける
パンパスグラスのリースだったら、リースワイヤーで巻き付けて留めるのですが、今回のススキは、量が少ない、パンパスよりも透ける、リースの径自体が小さい、などの理由から、リースワイヤーだとワイヤーが丸見えになってしまうような気がしました。そこで、それ自体は透明で見えないテグスで留めることにしました。

ワイヤーで作った円のどこかにテグスを結び付け、ススキの穂を、好きな長さに切って小さな束にし、テグスでワイヤーに巻き付けて留めます。

(白バックに同化してテグスが見えにくいです。ごめんなさい)
パンパスグラスのリースを引き合いに出して説明しますと、パンパスリースでやっていることのリースベースを円形ワイヤーに、リースワイヤーをテグスに置き換えた方法で作っていきます。

なぜほかのリースを引き合いに出して説明するかというと、テグスだと作成中の画像が撮れないからです。透明で撮りにくいこと以上に、「作成中に手を離せない」状態になります。ワイヤーだと、形を固定したら手を離してもほどけてきたりしませんが、テグスは糸と同じなので、手でぎゅっと締めておかないと、全部ばらばらにほどけてしまいます。
画像を撮ることに限らず、作成中に電話に出たり、家族に呼ばれて席を立つようなときには、ただ手を離すだけだと、それまで巻き付けてきたものが全部ばらけます。なので、途中で手を離すなら、一回結んで固定しないと、作業が元の木阿弥になります。
というわけで、テグス巻き付け中の画像がありませんので、最後まで巻いた画像を出します。

↑すでに吊り下げ用のリボンを付けています。小さいので、シンプルにしようと、ススキの穂と同じく茶色系の細いリボンで吊り下げます。
ススキの穂を一束ずつ取って付けるときに、すごく適当な長さと量にしてしまったため(要するに作者の大雑把さが出るのです)、変な飛び出しがあったり、厚みにもむらがあります。これを調整して出来上がりにします。、
微調整して、出来上がり
微調整は、「余計なものをカットする」方法で行いました。「足りないところに増やす」作業をするには、リースが小さすぎると思ったからです。後から挿しこんだものをうまくごまかすのは、ある程度の作業がしやすい大きさや、ごまかしやすい素材が無いと難しいです。
で、出来上がったのが下の画像です。

あちこちに鋏を入れて、飛び出しを取り、厚すぎるところを薄くしてみました。
もうちょっと整えられた気もしますが、気軽に作った小さいリースですので、この辺にしておきました。